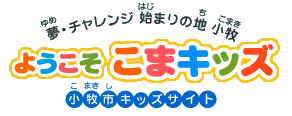歴史(れきし)
更新日:2020年08月26日
小牧の歴史年表(れきしねんぴょう)
旧石器時代(きゅうせっきじだい)から古墳時代(こふんじだい)
| 時代(じだい) | 年 | 小牧のできごと | 日本のできごと |
|---|---|---|---|
| 旧石器(きゅうせっき)時代 | 紀元前(きげんぜん)1万年ころ | 小牧山に人がくらした跡(あと)があった | |
| 縄文(じょうもん)時代 | 紀元前(きげんぜん)6千年ころ | 小木(こき)の織田井戸(おだいど)・北外山(きたとやま)の浜井場(はまいば)に人がくらした跡(あと)があった | |
| 弥生(やよい)時代 | 200年ころ | 北外山(きたとやま)に銅鐸(どうたく)があった | 卑弥呼(ひみこ)が中国に遣(つか)いを送る(239年) |
| 古墳(こふん)時代 | 300年ころ | 小木(こき)に宇都宮神社古墳(うつのみやじんじゃこふん)がつくられた | |
| 600年ころ | 野口大山(のぐちおおやま)に横穴式(よこあなしき)の古墳(こふん)がたくさんつくられた | 大化(たいか)の改新(かいしん)(645年) |

北外山(きたとやま)で見つかった銅鐸(どうたく)

宇都宮神社古墳(うつのみやじんじゃこふん)
飛鳥時代(あすかじだい)から江戸時代(えどじだい)
| 時代(じだい) | 年 | 小牧のできごと | 日本のできごと |
|---|---|---|---|
| 飛鳥(あすか)時代 | 700年ころ | 大山に大山寺(おおやまでら)がつくられた | 大宝律令制定(たいほうりつりょうせいてい)(701年) |
| 平安(へいあん)時代 | 900年ころ | 篠岡地区(しのおかちく)で陶器(とうき)がたくさんつくられた | |
| 1152年 | 大山の大山寺が焼(や)かれた | 保元の乱(ほうげんのらん)(1156年) | |
| 室町(むろまち)時代 | 1444年 | 西尾道永(にしおどうえい)が大草に大草城(おおくさじょう)をつくった | |
| 戦国(せんごく)時代 | 1563年 | 織田信長(おだのぶなが)が小牧山城(こまきやまじょう)をつくり、城下町(じょうかまち)をつくった | |
| 安土桃山(あづちももやま) 時代 |
1584年 | 小牧・長久手(ながくて)の合戦(かっせん)で羽柴秀吉(はしばひでよし)と徳川家康(とくがわいえやす)があらそった | 本能寺(ほんのうじ)の変(へん)(1582年) |
| 江戸(えど)時代 | 1608年 | 小牧村で検地(けんち)がおこなわれ、土地の広さが測(はか)られた | 江戸幕府(えどばくふ)ができる(1603年) |
| 1650年 | 木津用水(こっつようすい)ができた |

大山廃寺跡(おおやまはいじあと)

小牧山城の石垣(いしがき)
明治時代(めいじじだい)から平成時代(へいせいじだい)
| 時代(じだい) | 年 | 小牧のできごと | 日本のできごと |
|---|---|---|---|
| 明治(めいじ)時代 | 1873年 |
小牧山が「小牧公園」(こまきこうえん)としてつかわれはじめた |
明治維新(めいじいしん)(1868年) |
| 1905年 | 大山に大山焼陶器株式会社(おおやまやきとうきかぶしきがいしゃ)ができて焼(や)きものがたくさん作られた | 濃尾大地震(のうびだいじしん)(1891年) | |
| 昭和(しょうわ)時代 | 1930年 | 尾張徳川家(おわりとくがわけ)が小牧山を小牧町に寄附(きふ)した | 満州事変(まんしゅうじへん)(1931年) |
| 1955年 | 小牧町、味岡(あじおか)村、篠岡(しのおか)村が合併(がっぺい)して、小牧市ができた | ||
| 1963年 | 北里(きたさと)村が小牧市と合併(がっぺい)した | ||
| 平成(へいせい)時代 | 1989年 | 現在の名鉄小牧線小牧駅(めいてつこまきせんこまきえき)ができた | 阪神・淡路大震災(はんしん・あわじだいしんさい)(1995年) |
| 2005年 | 市制50周年(しせい50しゅうねん) | ||
| 2013年 | 織田信長小牧山城築城450年(おだのぶながこまきやまじょうちくじょう450ねん) | 東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)(2011年) |

小牧市ができたときの写真

小牧市制50周年記念式典
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会事務局(きょういくいいんかいじむきょく) 文化財課(ぶんかざいか) 文化財係(ぶんかざいかかり)
小牧市役所(こまきしやくしょ) 本庁舎(ほんちょうしゃ)3階(かい)
電話番号(でんわばんごう):0568-76-1189 ファクス番号(ばんごう):0568-75-8283