地震のメカニズム
更新日:2017年08月31日
地球の構造について
地球は直径約12,740キロメートルの大きさの球状で、大まかに分類すると外側から地殻、マントル、核の3つに分かれている構造となっています。
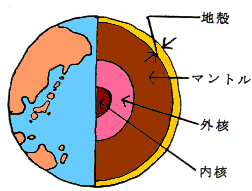
地殻
マントルから噴出した物質が、変化して重なったものにより構成され、マントルの上に浮いているような状態でできています。
プレート
地殻を乗せたマントルの固い板をいいます。
マントル
地殻と核の間にある層のことで、アルカリ系の岩石から構成されていて、年間数センチというゆっくりとした速さで動いています。
核
地球の中心部にあり、内核と外核に分かれていて非常に重い物質から構成され、内核は固体、外核は高温の液体ではないかといわれています。
地震の用語について
地震
地殻やマントル内で自然に起こる急激な変動と、その変動によって発生する地殻の弾性波動で地面が揺れ動く現象のこと。
断層
地殻の中にできた割れ目を境にして両側の地盤が互いにずれているもの。
活断層
断層の内、現在から約200万年前までに活動した断層のこと。

活断層
地震波
地震によって発生した振動が地球内部を伝わっていく時の波のこと。
震源
地震波が地球内部の1つの点で発生したとするとその点のことをいう。
実際には、地震の源が1つの点で発生することはないので、ある程度の広がりを持っていてこれを震源域といいます。
震央
震源の真上の地表の地点のこと。
液状化現象
砂地盤が地震の衝動で、液体のような状態になる現象。
つまり、砂地盤が地震の影響で一瞬のうちにずれる際、砂の中に含まれる水の圧力が急に上昇することによって、水を含んだ砂全体が液状化し、泥水が地表へ噴出すること。
この現象は、砂と地下水がある地盤に限って発生します。
震度
ある場所における地震動(地震によって発生する地面の振動)の強さの程度を表すもので、平成8年10月にこれまでの8階級から10階級に見直されました。詳細については、「震度階級」をのぞいて下さい。
マグニチュード
地震全体の規模(大きさ)を表すもので、Mとも記します。Mが1違えば、エネルギーは32倍、2違えば1,024倍も違います。
ガル
加速度の単位で地震の揺れの強さを示します。発見者「ガリレオ・ガリレイ」の名にちなんでつけられています。
地震によって地面は刻々と揺れ動き、速度も刻々と変化しています。
その際、毎秒1センチメートルの速度が1秒間に変化する量を示し、南北方向、東西方向、上下方向で表します。
一口メモ
震度とマグニチュードの違いを説明します。電球に例えると、電球のワット数がマグニチュードで、電球によって照らし出されたある場所の明るさが震度です。ワット数が高いほうが必ずしも明るいとは限りません。距離が遠ければ、ワット数が低い電球の近いところより暗くなることもあるからです。
このように、震度とマグニチュードは、 必ずしも比例するものではありません。 「地震防災の心得 備えて賢く生きる」
自治省消防庁震災対策指導室 監修より内容文一部抜粋
地震の種類
海溝型地震
日本列島について考えてみると、東太平洋から沸き上がった太平洋プレートが、年間数センチメートルの速さで、数万年かかって日本近海に達し、ユーラシアプレートの下に沈んでいきますが、この時、ユーラシアプレートの下の部分を摩擦の力で下にひきずり込んでいきます。
ユーラシアプレートの端はこれにより年間数センチメートルずつひずみ、100年から200年たち数メートルのひずみになると、耐えられなくなり、ユーラシアプレートがはね返ることによって発生する地震のことをいいます。
内陸型地震・直下型地震
陸地内に発生する地震で、陸地の下のプレートのひずみの力を活断層が部分的に吸収する際に活断層がずれて動くことによって起こります。
海溝型に比べて一回り小さく、一般的にはマグニチュード6.5から7.5どまりといわれていますが、震源が内陸であるために大きな被害をもたらします。
特に内陸の直下の浅いところで起きた地震を直下型地震と呼びます。突き上げるような上下動と激しい水平動が入り混じり、ものすごい振動となり、局部的に大きな被害が発生します。
前震・本震・余震
地震によっては、比較的小さな地震が起こった後、大きな地震が発生する場合があります。そして、その地震相互の時間感覚が短く震源の位置が近い場合は前者を前震といい、後者を本震といいます。更に、引き続いて起こる数多くの地震を余震といいます。今までの観測では、余震は多くの地震にみられ、大きな地震になるほどその数も多くなります。
これに比較すると前震を伴う地震はきわめて少ないのですが、小さな地震が繰り返し起こった後に本震が来ることが多いので、警戒する必要があります。余震は本震よりも規模は小さいけれども、本震で非常に大きなショックを受けた直後でもあるので、心理的に与える影響が大変大きくなります。
震度の目安(気象庁震度階級関連解説表より抜粋)
震度が同じでも、様々な状況により被害が異なる場合があります。
震度0
- 人は揺れを感じないが、地震計に記録される。
震度1
- 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。
震度2
- 屋内にいる人の多くが揺れを感じる。
- 電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。
震度3
- 屋内にいるほとんどの人が、揺れを感じる。
- 棚にある食器類が音を立てることがある。
- 電線が少し揺れる。
震度4
- かなりの恐怖感があり、一部の人は身の安全を図ろうとする。
- 歩いている人も揺れを感じる。
- つり下げものは大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。
- 電線が大きく揺れる。
震度5弱
- 多くの人が、身の安全を図ろうとする。
- 一部の人は行動に支障を感じる。
- つり下げるものは激しく揺れ、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。
- 窓ガラスが割れて落ちることがある。
- 電柱が揺れているのがわかる。
震度5強
- 非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。
- 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。
- タンスなど重い家具が倒れることがある。
- 多くの墓石が倒れる。
- 自動車の運転が困難となり、停止する車が多い。
震度6弱
- 立っていることが困難になる。
- 固定していない重い家具の多くが移動、転倒する。
- 開かなくなるドアが多い。
- かなりの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
- 耐震性の低い住宅では、倒壊するものがある。
震度6強
- 立っていることができず、はわないと動くことができない。
- 固定していない重い家具のほとんどが、移動、転倒する。
- 戸が外れて飛ぶことがある。
- 多くの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
- 耐震性の低い住宅では、倒壊するものが多い。
- 耐震性の高い住宅でも、壁や柱がかなり破損するものがある。
震度7
- 揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。
- ほとんどの家具が大きく移動し、飛ぶものもある。
- ほとんどの建物で、壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する。
- 耐震性の高い住宅でも、傾いたり、大きく破壊するものがある。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 防災危機管理課 防災危機管理係
小牧市役所 本庁舎6階
電話番号:0568-76-1171 ファクス番号:0568-41-3799

