小牧の中小企業振興を考える車座会議を開催しました
更新日:2017年12月12日
地域の各主体が集い、中小企業振興について考える「車座会議」
小牧市では、中小企業振興の理念を示した「小牧市中小企業振興基本条例」を平成28年7月1日に施行しました。
このたび、条例施行から1年の現状を踏まえ、中小企業振興の今、そしてこれからについて地域の皆さんが一緒に考える「車座会議」を開催しましたので、会議で発表された意見などについてお知らせします。
【小牧の中小企業振興を考える車座会議】
●開催日時 : 平成29年11月21日(火曜日)午後1時30分から
●開催場所 : 小牧市役所 本庁舎6階 601会議室
●参加者 : 31名 (中小企業者14名、金融機関職員9名、大学関係者4名、商工会議所関係者
2名、市職員2名)
●コーディネーター : 名古屋経済大学 経済学部教授 峯岸信哉 氏
●開催目的 : 小牧市中小企業振興基本条例の理念を実現していくため、地域の各主体が
中小企業の現状を共有、意見交換を行い、その結果を各主体がそれぞれの
組織に持ち帰り、フィードバックすることで、今後の取り組みにつなげる。

当日は、30名を超える方々にご参加いただきました。まず市担当者から小牧市中小企業振興基本条例の説明、中小企業振興をめぐる現状についての事前アンケート結果の説明をした後、コーディネーターの峯岸教授の舵取りのもと、グループに分かれて活発な議論が行われました。

今回の車座会議では、小牧市中小企業振興基本条例検討委員会の副委員長として条例制定にも関わっていただいた、名古屋経済大学経済学部の峯岸信哉教授にコーディネーターをお願いしました。
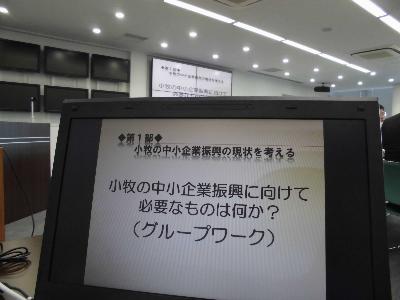
グループワークのテーマは、「小牧の中小企業振興に向けて必要なものは何か」。非常に大きなテーマのため、漠然とした議論とならないよう、切り口として「課題」「企業の主体的努力」「各主体の取組」「地域貢献」を提示し、これらの視点から意見を出してもらいました。
小牧の中小企業振興に向けて必要なものは何か

「中小企業者」「金融機関」「大学・商工会議所・市」のグループに分かれ、グループごとで様々な意見が出されました。休憩を挟み、グループワークの結果について、各グループから発表してもらいました。


各グループからは、次のような意見がありました。
◆中小企業者◆
【課題】
・人材の採用、育成、企業の発展をして、社員の生活を守る必要がある。
・人口減少に伴う人材の確保が難しい。後継者がいない。
・産業のグローバル化により地域のつながりが希薄となり、地域内循環が薄くなった。地域経済を主として担ってきた零細・小企業の環境が悪化している。
・今の仕事に手一杯で余裕がなく、自社のPRが必要と感じても実施が難しい。認知度が低い。
・社員数が少ない。研究開発に人を割けない。
・経営計画書の浸透が大事。
・売りとなる強みが明確ではない。
・自社の強みを上手く伝えられない。
【企業の主体的努力】(自らの取り組みとして必要なもの)
・地域での雇用、企業発展や設備投資を行う。
・「行政に何をしてもらう」のではなく、自らが主体性を持って地域振興に携われるよう意識を改革する。
・販路の開拓(新業態の販路)
・新製品の開発
【各主体の取り組み】(他の主体に要望すること)
・中小企業の社員の生活を守る仕組みづくり
・地域の人材を採用した場合の待遇制度
・中小企業が単体で今まで以上の発展を見込むということはかなり難しいことを理解してほしい。
・事業承継に関するサポート(後継者の側の学習)
・同業者間の連携・グループ・つながり
・大学で学生に対して中小企業のやりがいを伝えてほしい。
・自社の強みを外部へ発信する手助けをしてほしい。
・車座会議を実施するのはよいが、市の職員の参加が少ない。また意見が書かれたものをコピーしている暇があったら、議論に参加するなど、積極性がほしい。
・今回の車座会議のような各主体が集まって話ができるような場を定期的にもってほしい。
【地域貢献】
・車座会議への出席
・地域の活動に意識を向けること。
◆金融機関◆
【課題】
・金融機関内での業務に対する評価と振興活動がリンクしていない。(振興活動は評価に直結しないため後回しになりがち)
・各金融機関が持つ本部機能が活かしきれていない。
・事業承継等の提案が本当にできているか。(技術力があり収益性もあるが、後継者難の会社は多い)
【各主体の取り組み】(金融機関としての取り組み)
・職員の人材育成(真のニーズ把握、潜在ニーズを分からせる。本部機能の活用方法の教育)
【地域貢献】
・参加型の地域活動には、極力参加する。(顧客との共通の話題が持てる)
【中小企業者に求めること】
・その他支援も含め、トータルで金融機関を決めてほしい。(金利のみで判断をしないでほしい)
◆大学、商工会議所、市◆
【課題】
・大学卒の人材が、中小企業に入らない。(人材を送り出す大学側としては、大企業・中小企業という規模の差はあまり関係がなく、「入社したら、その会社で何ができるのか」が重要であり、「誰でもいいから入社して」という姿勢だと、入社しても続かず離職してしまう場合が多い)
【各主体(中小企業者以外)に求めること】
・学生の親に、中小企業への就職に反対という考えがあるため、行政が啓蒙を図ってほしい。
・中小企業が求めている人材(こういう人材がほしい)の情報を集約し、リスト作成
【中小企業者に求めること】
・大学側へのアプローチ(OB、OG、キャリアセンター、教授など活用してほしい)
・企業の名前や商品を、ホームページなどを通じ、積極的に発信
・大学で出前講座を開けるくらいの関係を構築
キーとなるのは 「 情 報 」、「 連 携 」
各グループから発表された内容を受け、コーディネーターの峯岸教授が、次のように議論を整理されました。
・企業の発展のために必要なキーワードは「ヒト・モノ・カネ」と言われるが、モノについては小牧は十分にあると思う。
・小牧の中小企業振興に必要なものは、ヒト・カネともう一つ「情報」だと思う。情報をいかに出していくか、あるいは得ていくのかが一つのキーとなる。
・情報に関しての先ほどの意見として、中小企業側からは、「自分たちがこういうことをやっているとアピールすることが難しく、時間も無い。どういう所に出せばよいのかも分からない。」と情報を出すことの難しさがあった。
・中小企業振興のための施策は市も行っているし、金融機関なども取り組んでいる。しかし、そうした情報をどこに行けば得られるのか、取りにいきずらいということもある。
これを受け、各グループからは、
・中小企業と大学がコラボして、中小企業が何をしているのかといった紹介を学生にできると良い(中小企業者)
・中小企業が何を作っているのか、人材をどう育てるのか、企業の名前もわからないのが現状であり、そうした情報の発信が必要。そのために情報のリストアップをして大学等に提供したらどうかという意見もある。一方で、PRするにも、中小企業側にそれを行う人手がいないという声もある。その部分を学生にやらせてみるという方法もある(商工会議所、大学)
・大学としても、学生が企業の現場を見て体験できる就業体験(インターンシップ)に力を入れており、中小企業の魅力を伝えるためにも、ぜひ、地元の中小企業に受け入れをお願いしたい(大学)
・顧客の事業内容・状況について、どれだけ深堀りし、理解できているのかに尽きる。これからの課題と思う(金融機関)
・インターンシップの話もあったが、地域・社会への貢献がこんなに楽しいんだということを学生が実感できるような取り組みをお願いしたい(中小企業者)
・中小企業の経営者も年齢を重ね、10年、20年も経つと、最新の情報から取り残されてしまうため、事業に活かせる情報を得ることのできる交流ができればよいと思う(中小企業者)
・高齢者の活用という点で人材バンクのようなものがあるのかもしれないが、横のつながりが分断されていることにより知らなかったりで活用されていないことがある。例えば市の組織を見ても、中小企業振興に関わるのは商工振興課だけでなく、教育部門も関係するはずだし、そういう横断的に情報を共有できるとよい(中小企業者)
などの発言があり、最後に、峯岸教授が次のようにまとめられました。
・中小企業振興には、いろいろな側面があるが、一つの考え方として、「ヒト・カネ・情報」がキーになると思う
・このうち、「情報」を上手くアウトプット、インプットしていければ、「ヒト」に対してのアピールもできるし、金融機関に上手く伝われば「カネ」の部分にもプラスにつながる
・情報を上手く出したり、入れたりするには、「連携」がキーになる。
・中小企業は、日々努力をしていると思うが、少し意識を変えてほしいのは、短期的な利益ばかりを見るのではなく、5%でよいので、中・長期的な視点を持つよう意識する必要がある。中・長期的な情報を出したり入れたりするために何ができるのか、どこと手を組めるのかということを考え、行動することにより、発展していくための土台づくりにつながる。
・中小企業振興には、横のつながりが重要であり、企業同士、また金融機関や行政、大学とのつながりも大事。今回の車座会議が、つながるきっかけになればと思う。
今回、初めての試みとして、この車座会議を開催しました。
限られた時間の中で、議論は尽きませんでしたが、コーディネーターの名古屋経済大学の峯岸教授、そして忙しい時間を割いてお集まりいただいた中小企業者・支援機関の方々のおかげで、中小企業振興について地域で考える一つのきっかけになったのではないかと思います。
今後も、小牧市では、地域社会の発展にも寄与する中小企業振興に努めてまいりますので、地域の皆様におかれましても、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

